本部
![]()
幸福を探し始めた日

掲示板
-
 依頼前の挨拶スレッド
依頼前の挨拶スレッド
最終発言2017/02/26 19:48:16 -
 相談卓
相談卓
最終発言2017/03/01 03:21:58
オープニング
●
悩み事とは距離を置けない相棒のような存在だ。人間は何かを満たすために悩み、それが原動力となる。像だって。水飲み場を探すために当てのない道を歩いている。宇宙が存在すれば、誰もが悩みを持つ。
ロボットだって。
犬型四足歩行ロボットのスチャースは深夜スリープ状態に入る際に、自動的に記憶の整理をしていた。今戦っている対テロ組織の情報を纏めたり、無駄な記憶の削除をしたり。
何ヶ月も前からだ。彼の記憶には見たことのない景色が浮かんでいた。
十歳もない女の子と、それを抱きしめる三十歳くらいの女性の映像だった。二人が綺麗な部屋の中で笑いあっていた。
部屋の中には三人目もいた。それはスチャースが見ている映像自身なのだ。誰かの視点で記録されているこの情報は、無駄な記憶として処理されなかった。いい加減スチャースは、映像が何なのかを確かめる時期に差し掛かっている。
「坂山、すまないがしばらく席を空ける」
休暇申請は突然で、坂山は目を丸くした。通信士の座る椅子の上で。
「どうしたの?」
「しばらく自分がいた研究所へと戻る。やりたい事があるのだ」
「そう。別にいいわよ。やりたい事があるなら、やらなくちゃね。何なのかはわからないけど」
「私も説明しづらくて困る。ノボルが外食から帰ってきたら、伝えておいてほしい」
坂山の英雄、ノボルは今朝寝坊したことが災いとなって朝食を食べられなかった。非常にお腹が空いて、昼休憩前の食事が仕方がないものとなった。
「気をつけてね、スチャース。まあ、改良されたあなたなら大丈夫でしょうけれど」
「分かっている。それではな」
元気に尻尾を振ってスチャースは通信室から外に出た。坂山は扉が閉まるまで手を振っていた。
通信室には大体、スチャースかノボルかどちらかがいた。
ちょっとした孤独感を得た。懐かしさを感じさせる。
●
スチャースが休暇をしてから二日経った。人探し、事業の手伝い等の簡単な任務を対応していた坂山は、いつになったら戻ってくるのかと想像していた。
用事の理由も分からない。帰ってきたら問い詰めてやろうと考えていた矢先、坂山の端末機器に一通のメッセージが届いた。スチャースからだった。
画像が二通添付されている。廃れた研究所の一室の画像。それから、こちらも廃れた三階建て一軒家の外観を撮影した画像だった。
その下にS.O.Sと書かれていた。
「坂山、これは……」
「嫌な胸騒ぎはしたのよ。的中してほしくない嫌なのが。……すぐにエージェントを集めなくちゃ」
「でも、危ないよ。もし危険な任務だったら!」
「何のためにエージェントは存在するのよ。困ってる人たちを助けるためでしょ」
何が起きているのかは分からない。坂山も、得体の知れない場所にエージェントを送る不安はあった。スチャースは、何が起きているのかを説明する余裕がなかったのだろう。ただ不気味だった。この廃れた、明かりのない研究所には机があって――
その上に誕生日ケーキが乗っていた。
「皆には何があったのか調査してもらわないと……。この不気味な研究所と一軒家で、何が起きたのか」
画像だけでも伝わった。ここは、一般人が訪れてはいけない場所なのだと。
●
この真実をどう受け止めればいい?
私はスチャース、四足歩行のロボットだ。人工知能を持っている。
幸福を探し続けてもう何年も経っているが、この任務について今議論する暇はない。私は常日頃、自分の生誕は気にならなかった。
どうして生まれたのか、幸福を探すために生まれたのだ。
研究所を調べて見て、その事実は揺るがなかった。幸福を探すために生まれた。ではどのようにして生まれたのか? この研究所とはなんなのか? 私を作った主人とは。
疑問は数を知らなかった。私という宇宙が作られた日、何が起きた?
なぜ幸福を探すのか、なぜ主人……博士はその感情を得たのか。答えがあまりにも、研究所に残されすぎていた。私は動揺した。
博士は幸福探しの旅を知っていたのだ。
そして私自身が、博士だったのだ。
解説
●目的
犬型ロボット、スチャースの救助。
●スチャースの現在
エージェントが到着した際、スチャースは研究所に逃げ込んでいる。声を出したら奴らに知られるために、スチャースは跡を残して、見つけてもらうための準備はしている。
無事に発見できれば、何が起きたのかを全て説明してくれるだろう。
●廃れた研究所
スチャース生誕の場所。坂山の所に来る前は、ここで暮らしていた。
個人の研究所で、生活空間も併設されている。研究所の入り口はマンホールのような蓋であり、発見には多少の時間を要するかも。(以前この研究所を舞台にしたシナリオに参加したプレイヤーがいれば、案内してくれるだろう)
階層の形は同じで、正四角形が重なっている構造だ。地下にいくほど面積が小さくなっている。
一階はパーソナルスペースで、研究する場所はなく、一般家庭を思わせる階層。ワンルームである。
一階中央の階段を下に下り、二階から研究施設になる。二階は三つの部屋が連なっている。
三階は二つの部屋があり、片方の部屋が病室に、片方の部屋が助手の個人室となっている。
●廃れた一軒家
二階の研究施設にある隠れた通路を通って到着する場所。
この一軒家も個人の研究施設だったが、今は愚神に汚染されて中にいる人型のロボット達は従魔となっており、住人は死亡している。
スチャースはこの一軒家に用事があった。記憶に残っている映像と場所が一致していたからだ。
●汚染されたロボット
広い一軒家にはライヴスの弾丸を放つ銃を持ったロボットが徘徊する。ロボットに一度見つかると警笛が鳴らされ、あらゆる所から侵入者を排除すべく戦闘が始まる。彼らを開放するには愚神を倒すしかない。
元々は、善良なロボットだった。
●愚神
支配者は三階の書斎に座っている。エージェントに見つかると、彼は部屋の中にある戦闘装置(固定砲台等)を全て起動して、エージェントを襲う。彼自身に戦闘力は無い。
リプレイ
研究所がある山の道のりまでに、小さなロシアの町がある。山の洞窟内には豊富な鉱物がなっているために、それを売買して安定した資源を確保できている。
「ああ、あの亡くなったオブルグさんの家ね」
町長を訪ねていたのは晴海 嘉久也(aa0780)であった。彼の隣にいるのは紫 征四郎(aa0076)で、傷ついた身体ながら「何かできることは」と模索して律儀にも、彼の隣でメモを取っていた。
「どのような目的で、等は聞いておりますか」
「山の所有者は私なもんだから、勿論聞いたよ。人工知能の研究だとねえ。かれこれもう十年経つかな、研究所ができてから」
「そんなに、ですか」
「亡くなったと報せを聞いた時は正直、本当に残念だった。彼は温厚な人で、優しかったからなあ」
年をとった男性らしく、彼は手を震わせてロシアンティーを口に入れた。カップから口を離した後もう一度「残念だ」と言った。
「リンカーさんが研究所について訪ねてきたってことは、何かあったんだろうね」
「はい」
晴海はこの町にきた経緯を、隠さず全て話した。
「じゃあ、あのチビはまだ生きていたのか」
「スチャースをご存知なのですか」
「よくオブルグさんの家には遊びにいってな。彼がこう、ロシアンティーを用意してくれている間や空いた時間にスチャースと遊んだものだよ。亡くなったと聞いていたから。ああ、まだいるのか。で、スチャースが危機的状況だと」
「何があったのかわかりますか?」
紫が訊いた。町長は顎に手をおいて衰えた想像力を使っていたが、首を横に振った。
「分からんな。少なくともこの町に被害は出ていないからなあ。ただスチャースは絶対に嘘をつかん」
「私もそう思います。研究所の所有者は以前と今とで変わっているのか、尋ねても良いでしょうか」
「今も昔も私だとも。この町に越してきた時オブルグさんはお金がなかった。私に多額の借金をして研究所を立てたから、事実上所有者は私なのだな。ちなみに、借金は全て払ってもらった。十年かけてな」
オブルグがどれだけ律儀な男であったかを説明し終えた時に、紫の端末機に連絡が入った。他のエージェントが集ったのだ。
「貴重なお時間、ありがとうございました」
晴海は礼をした。
「頼んだ。あの研究所には思い出が詰まってるんだから。何とかして、助けてほしい」
町長の握手は力が強かった。
●
「スチャースって、どんな人なの?」
六道 夜宵(aa4897)はスチャースと目を合わせたことがなかった。研究所までの山道を登りながら、隣にいた橘 由香里(aa1855)に尋ねた。
「とりあえず人じゃないわ。犬型のロボットね」
「へえ、可愛いね!」
「会ってないのに可愛いっていうのが分かるのね」
「勿論! 動物っていうだけで可愛いよ。私がそういうんだから、間違い無し!」
雪山の木はほとんど白く、太陽も見えなかった。雪は降っていないが、雪の海を歩くのは苦労するのだった。こんな時でなければ雪合戦や、雪だるまを作って楽しめたのだが。
「スチャースさんはただのロボットではないのです。それはもう、歴史的に大きな進化を遂げたロボットなのです」
エスティア ヘレスティス(aa0780hero001)は博物館を案内する係員のように言った。
「喋るんです」
「ほう!」
係員の説明で真っ先に感嘆を表に出したソーニャ・デグチャレフ(aa4829)は、エスティアに近寄った。
「そして自分で考えて、行動することもできるのです」
「ほう、ほう。思考する犬型ロボットがいるとはやはりこの国はライヴス先進国であるな。興味深い、早くスチャースとやらに会ってみたくなったぞ」
列の最も前で歩いていた赤城 龍哉(aa0090)は以前来た時の記憶を頼りに道を進んでいた。確かこの辺りの木は不規則になっていて、一本だけ異様に大きかったのだ。それと雪の降り積もる量が不自然な場所もあるはずだ。
「よし、ここだな」
積もった雪を払い、赤城は取っ手を探す。冷凍庫に手を入れているようだった。取っ手を掴んだ赤城はすぐに手前に開いて、研究所の扉を開いた。
奥を覗き込んだカグヤ・アトラクア(aa0535)は、手を擦り合わせて言った。
「いよいよスチャース量産の為、スチャースの生まれた研究所に潜入じゃな!」
「量産ってカグヤさん、お節介がたくさん増えたら大変でしょうに」
「わらわがお世話をするから問題なっしんぐじゃ」
クー・ナンナ(aa0535hero001)は小声で、「この前保健所から預かった犬達も結局ボクが」とぶつくさ言うもカグヤは全く気にせず、一人研究所の中へ進入した。
次にすぐ迫間 央(aa1445)が降りて、ノクトビジョン・ヴィゲンを装着した。
「先に私が奥を調べてきます。カグヤさん達は、安全が確認でき次第、後ろからついてきてください」
「分かったのじゃ。わらわはここを物色しておくとするかのう」
迫間は隅々まで調べて危険の皆無を知ると、次に地下二階へと続く階段を歩いた。その時には全員のエージェントが研究所に入っていた。
「さて、スチャースはどこにいるのやら」
「呼んだら出てくるかな? こっちは面識があるエージェントも一緒にいるんだし」
「いや、SOSとあったからには、敵の存在を考慮する必要がある。こっそり探そう」
「……それじゃ、この懐中電灯の明かりもヤバくない?」
一階はパーソナルスペースになっている。若杉 英斗(aa4897hero001)は懐中電灯を消して、棚の中に入っていたグラスカップを手に取りながら言った。夜宵はカグヤとは正反対の位置を物色しており、何か見つけたのか動きを止めた。
「あ、テレビゲーム機があるよ。これは……ちょっと前に流行った奴だよ。ここの博士はミーハーだったのかな」
「助手がやってたんじゃねえか」
もう居ないが、赤城はこの施設に助手がいたのを覚えている。まだ若いから、息抜きにゲームをしていたのではないか。
「コントローラーは二つあるよ。やっぱり博士もやってたんじゃないかな!」
「なるほどのう」
飯綱比売命(aa1855hero001)は頷いた。
「みーはーなわらわも知らないこともないのじゃが、ゲームにはえーあいというのがいるじゃろう。ある意味人工知能じゃ。それを見て学んだということも考えられるのう。うむ、納得のいく仮説じゃ」
「確かになあ。研究者って色んなところから学ぶんだな」
「知らない漢字を我が子が覚えたら、それはアニメとかゲームとかのせいじゃ。肝に銘じておくと良い」
茶化したような言い方をした飯綱比売命だったが、橘は本当に聞こえていなかったみたいだ。彼女は台所で、乾燥機に入れられた皿を無意味に見つめていた。
「目ぼしい物でも見つけたか?」
ソーニャが訊いた。
「いいえ、ちょっと考え事をしてたのよ。スチャースが心配で」
「貴公はスチャースと知り合いであったか」
「友達ね。結構付き合いは長いのよ。もう一年以上経つわ」
「長いな。それほどスチャースとやらは友達になりやすい奴ということか。益々会ってみたいな!」
橘は以前ここに訪れた時、幸福をスチャースに問われた。橘は答えられなかった。彼女にとって難しすぎる問いだったからだ。
その日から橘は考えるようになった。幸福とは何なのだろうと。暫く正解は見つからなかったが、考えることこそ重要なのだ。
「小官も友達になってもらうぞ」
階段を登って来る音が聞こえて、正体は迫間だった。
「地下二階の安全が確認された。ただ一部穴が空いていたから注意するようにな。何があったんだろうな」
「穴を開けた犯人は知ってるぜ。俺だからな」
スチャースを探していた赤城は迫間の方を向いて言った。
「まだ直ってなかったか」
「派手に暴れたみたいだな。とにかく気をつけるように」
以前ここで、人工知能を巡って町の宗教団体と一悶着あったのだ。宗教団体に関与しない男がいたが、それはまた別の話だ。宗教絡みの事件で赤城は、仲間のピンチを救うために床を破壊したのだ。
●
紫は一階の椅子に座って、迫間が撮影した二階の映像を繰り返し確認していた。ユエリャン・李(aa0076hero002)も側にいる。子供の宿題を手伝う母親のように、椅子に座らずに立っていた。
ビデオの開始は迫間が階段を下るところから始まっていた。階段を下るとすぐ左に地下三階に下る階段がある。直線的な廊下には三つの部屋があって、それぞれが研究所となっていた。迫間は一番左の部屋から調べたみたいだ。
「至って普通ですね……」
「丁寧に録画されているな。天井から地面まで満遍なく撮影されているのだ」
「スチャースがちょこっとでも映ってくれていると良いのですが」
「どうだろうな。スチャースを呼んだら出てきてくれるのではないか」
「敵がきてしまうかも……」
紫は慎重になっていた。
迫間は二つ目の部屋を調べていたが、間取りは先程と同じだが、床に穴が開いている。赤城の仕業によるものだ。迫間は時間をかけて穴を撮影した後に、部屋を見回り始めた。
「うーん。至ってフツウ」
「SOS、と送られてきたからには何か起きているのだろうが」
「うーん。送られてきた写真の場所が見つかると良いのですが。それと、二枚目の写真は一体どこにあるのかというのも。山を登っている最中は見つかりませんでした」
「そうだな――今日の君はいつもと比べて真面目だな。良い事だ」
「征四郎も由香里と同じで心配なのです。壊されちゃったって考えるだけで鳥肌が立っちゃうほどです」
三つ目の部屋も同じように調査を終えて、一階に戻ってくるところを最後に動画は終わった。紫は最初からまた再生した。会話もなく、無言でじっと画面を見つめていた。
ユエリャンは集中している紫を驚かせようかと無邪気な発想が出たが、今は控えておいた。
「むむ」
二つ目の扉を開く所だった。紫は動画を止めた。
「ちょっと暗くて分からないのですが、影みたいな物が見えませんか?」
モニターの中央よりも右よりの部分。穴の近くに影が映った。本当に黒くて正体は分からない。完全に扉が開かれる時にはそれは無かった。
紫はすぐに、迫間と通信を繋げた。
「今はどちらにいますか?」
「地下三階の階段を下っているところだが」
「良かったです。動画を見ていたのですが、ほらあの……穴です。迫間さんが二つ目の扉を入る時に穴の近くに影がありました。穴に吸い込まれるように消えてしまいましたが」
「もしもそれが敵なら、俺達の存在が気づかれたという厄介な話に広がる訳か」
「敵とは断定できません。ですが慎重に動いてください……」
「心得た」
紫は椅子の背凭れに寄りかかった。
重体であるという事は本来、家で安静にする期間を設けるべきなのだ。身体を動かさなければいいとは違う。頭も休める時期なのだが、紫は真剣に任務に取り組んでくれていたのだ。
集中から疲れが出たのだろう。ユエリャンは紫の肩をほぐした。
「お疲れだな。少し休憩するといい」
「ありがとうなのです。ですがまだ任務は終わってないので、征四郎はまだまだ頑張ります」
頑張り屋の紫は、優しく自分の頬を叩いて気合を入れた。まだまだ休んでいる場合ではないのだ。スチャースを見つけるまでは! ……とはいえ、まだ地下三階の動画は送られてきていないから、やる事には欠けるが。
●
カグヤはれっきとして、至って明瞭にスチャースの生誕の場所がここであると知った。地下二階、一番左側の扉がそうだったのだ。
別れて捜索しており、左側の部屋にいるのはカグヤとクー、晴海とエスティアだ。カグヤはキャビネットの中に仕舞われていた、束になった実験レポートを見ていた。
表紙にスチャースと書かれていた。
「実験は七年前から始まったようじゃな。日付がまさにそうじゃ。それで……失敗続きだったようじゃの」
「まあそうだよね。感情とかを持つ人工知能ロボットの作り方なんて想像もできないよ」
「興味深いのは途中、一度実験を放棄しているな。研究を始めて三年経ってから二年のブランクがあって、再びスチャースの作成に取り掛かっておる。ちなみに、作成方法はブランク前と後じゃ違うのう」
「どう違うのでしょうか」
晴海が訊いた。
「前はプログラムを使った人工知能の作成に尽力しておる。感情について調べ、機械だけを使って作っている。で、後はプログラムだけではないのう。人間の脳を使おうと試みていたようじゃ」
「それは……例えば、どのような実験に?」
「人間の脳とスチャースのチップを繋げて、移植に近い状態を作る。しかし失敗と書いておる」
レポートには図が描かれていた。二つのベッドがあって、人型ロボットの頭頂部と人間の脳が管で繋がれていた。
「昔スチャースは人型のつもりで作られていたのじゃな」
暫くは無謀な実験が続いていたが、とある一枚のレポート用紙を前にカグヤは止まった。その実験は、人間の脳をスチャースに完全移植するものだった。
「酔狂じゃな」
「嫌な想像が当たりそうですね。博士はもしかすると」
「さあてな。この実験の結果も失敗と書かれておる。――博士はそれ以降、寝たきりの状態になってしまったようじゃな」
レポートはそこで終わっていた。
感情という物の定義はまだ済んでいないのだ。小学生が掛け算も分からないまま三角関数まで覚えようとしているようなものだった。
「レポートには続きがあずはずじゃ。そうでなければスチャースは出来まい」
「探してみましょう――」
すると研究室の扉が開いて、迫間が戻ってきた。
「スチャースを見つけた。地下三階の病室にいたみたいだ。バースデーケーキも一緒に置かれていた」
「見つかったんですね、良かった。どこにいたのですか?」
「椅子に座っていた。俺たちが駆けつけたことを知って、隠れ場所から出て待ってくれていたらしい」
スチャースは二階の穴のある扉で隠れていた。いつ敵が入ってきてもすぐに三階に逃げられるようにその場所を選んだのだ。斥候役の迫間が入ってきたことを確認して、表に出てきた。
●
ラストシルバーバタリオン(aa4829hero002)とソーニャはスチャースを興味深く観察していた。更にソーニャは持ち上げてみせた。
「なんと、生きて動いておる。どういう仕組みであるか、頭を切開して小官に中を見せてもらいたいのである」
「これは中々、我々の興味を惹くものだ」
三階の助手室に全員が集まっていた。研究所は一応の安全が確保されて、警戒なく自由に動けるのだ。机の上にはバースデイケーキも置かれていた。
「お前も難儀な奴だぜ。SOSって、何があったんだ」
「これは私も初めて知ったことだが、研究所はとある廃屋に繋がっていた。私はその廃屋に用があって向かったのだが、従魔の巣窟になっていたのだ」
「研究所までは来てねえんだな」
「うむ」
スチャースの音量はいつもより小さかった。ラストシルバーバタリオンは明瞭に聞き取れたが、少し離れた赤城は所々の単語を読み取って話を理解していた。
「この誕生日ケーキ、誰が用意したんだろう」
六道が疑問の面持ちでケーキを眺めていた。
「日持ちしないし、最近用意されたものだよな?」
「誰が、何のために?」
「そりゃあ、やっぱり、お祝い?」
「スチャースはこのケーキ、何のことか分かるのかな」
腕から離れて机の上に乗ったスチャースは、何も分からないというように首を振ったのだが、同時に落ち込んで見えた。
「廃屋にもう一度行きたい」
私は自分のことを何も知らず、どうして幸福を探し続けているのか分からず、ただ生かされているだけだった。誰かの都合だけで生かされていた。
廃屋にいけば答えが見つかるはずなのだ。
スチャースはそう言った。
「私の我儘を許してほしい。ここで私が帰れば、君たちに面倒をかけることはないのだから」
その声は全員に聞こえた。
「幸福を探す次は、生きる意味を探す。大変じゃのう、お主は」
「愚かにも私は順番を間違えていた。先に生まれた目的を知るべきだったのだ」
「わらわも気になっていた。面倒事に付き合うのは別に、文句なしじゃ。恩返しも兼ねてな」
最初に異様な音を聞いたのはユエリャンであった。
「おチビちゃん、この音の正体がなんなのか分かるかな」
「音ですか?」
紫は眼を瞑って耳を澄ました。気付かなかったが確かに、響くような音が聞こえた。機械音のようで、音階が奏でられているみたいだが、滅茶苦茶な不協和音だった。
「こちらまで近づいてきていたか」
「どういう事ですか、スチャース」
「敵だ。奴らは恐らく、私の声に反応した。今まで音量を縮めていたが……油断して、元に戻していた」
音は少しずつ大きくなっていく。
「こっちに来てるわ」
「二階へ避難しよう。ここは危険だ」
スチャースが先頭となって三階の助手室から出て、二階にあるスチャースが生まれた場所へと戻ってきた。
彼は扉から入って真正面に見える壁の前で静止すると、音が鳴って壁が左右に開き始めた。どうなっているんだ。
「おいおい、こりゃ一体なんだ?」
「事情は後で説明する。ひとまず退避が最優先だ。急ごう」
スチャースの後ろに、護衛するように迫間がついてエージェント達は互いの背中に続いた。殿を務める晴海は、研究所と通路の境界線を跨がないカグヤに言った。
「急ぎましょう、カグヤさん」
「わらわはやりたい事がある。追手についてはわらわが何とかしておくから、続きは任せた。終わったら向かう」
「気を付けてくださいね。何かあったらすぐに連絡を」
「分かっておる」
自動的に壁が閉まって、カグヤは研究所に残された。
「何か面白い物でも見つけたような顔してる」
「間違っちゃないのう。マクランという助手の日記帳を見つけたのじゃ。調べたいことは山積みであるし、向こうには迫間や赤城、紫もいる。信じても損はない面子じゃろう」
調べ事の続きをするために、カグヤは助手の部屋へと戻った。既に先程の不快な音は小さくなっている。スチャースの音を追っているのだろう。
●
延々と続くような暗闇は前にも後にも続いていた。飾りのない一本道で、小さな電球が足元を照らしてくれている以外に灯りはない。壁も床も無機質で、トンネルにそっくりだった。
「この一本道は廃屋につながっている。私が、坂山の携帯に送ったあの画像の廃屋に」
紫はユエリャンの手を握っていた。
「首謀者は誰で、今どこにいるのかわかりますか?」
「……分からない」
「君でも分からないことがあるのだな。なんでも知ってる天才ロボットじゃないわけか」
「うむ。何も分からないのがここまでもどかしいとは、思わなかったものだ」
「あ……、もう少しで到着するみたいです」
鷹の眼を使っていた紫は、通路の出口が見えていた。相変わらず暗闇が続く道の最後には堅い扉があった。
五分が予想だったが、実際には三分だ。
「迫間、開けてほしい」
扉にはドアノブがついていた。犬のスチャースには捻ることができず、ここばかりは人に頼るしかない。迫間は扉を開けた。
「廃屋の地下だ」
といって、スチャースは先に廃屋へと入った。地下は倉庫番になっていて、あらゆる雑多な荷物が並べられている。ダンボールの箱が多く、陳列棚にもいくつかガラクタが置かれている。
「ここから先、私は声を出せない。代わりに端末にて会話を行うことにする。……面倒だが、奴らに気づかれないためだ」
「気づかれたら厄介な事になるんだね」
元気な六道にとって騒ぐなと言われるのは過酷だ。
「最悪口枷を使うしかないかなあ。静かにできる? 夜宵」
「勿論!」
若杉は彼女の口を掌で抑えた。
「語尾にビックリマークが付くような声で喋るのはノーグッドだな」
地下倉庫を探索していた橘は、ダンボール箱のガラクタの中に気になる部品を見つけていた。
「これ、スチャースの耳と同じ形状をしていると思わない?」
「本当であるな。先ほど沢山触らせてもらったからすぐに分かるぞ」
「他にも似たような部品はたくさん……。これを知ったらカグヤさん、喜ぶんじゃないかしら」
「幾つか持ち帰っても良いのであろうか。一家に一台スチャース、小官の家にもな」
「その話は後ね」
橘はスチャースを呼ぼうとして倉庫内を見渡した。スチャースを見つけたが、一箇所をずうっと見続けていた。座りながらだった。
「どうかしたの?」
スチャースの視線を奪っている物の正体は棺だった。棺の上には写真が置かれている。棺は二基あった。片方の写真は女性で、片方の写真は男の子だった。橘は手を合わせて日本式のお祈りをすると、しゃがんで写真を調べた。
写真にはそれぞれ名前が書かれてある。女性の方には「ユリヤ」と書かれていた。
子供には「スチャース」と書かれていた。
橘の端末にメッセージが届いた。それはスチャースからだった。
『私には分からない事だらけだった。今もまだ、何も分かっていない。これを見ても何も思い出せないし、感覚もない。
しかし、この廃屋を隅々まで調べなければならないという簡単なことはわかった。オブルグ研究所と繋がったこの廃屋を』
「そうね」
次にスチャースは、全員の端末にこう送った。
『地上に続く階段はこっちだ。だが、敵の数が多い。見つからずに移動するには少人数での行動が望まれる』
「それなら俺が行こう」
隠密行動に一番適するのは迫間であった。彼の申し出に反対意見を示す者は一人もいない。
「そんじゃ俺たちはここで、何かあった時のためにスタンバっとくぜ。迫間さん、いつでも援護にいけるからな!」
「助かる。紫はまた、動画を確認する準備をしていてもらいたい。見逃しをしないように」
「わかったのです」
階段は部屋の左奥に控えていた。短い間隔の段差を登る前に、スチャースは前左足で迫間を鼓舞した。彼なりの「頑張れ」という合図だった。頷いた迫間は、一歩一歩階段を登っていくのだった。
●
迫間は慎重に進んでいた。階段を登った先にあったのは梯子で、登る途中に天井に当たったが取っ手がついていた。天井が扉になっていたのだ。ゆっくりとそれを開くと、微かな光が入り込んできた。
少しだけ開いた隙間から空間を見渡してみて、そこがリビングであるとわかったのはキッチンが見えたからだ。
「可愛らしい従魔達ね」
マイヤ サーア(aa1445hero001)が言った。リビングにはポップ調で、ニコニコと笑ったロボット達が徘徊していた。身長は約百五十センチ、ピンク色のエプロンを着けている。
「家政婦ロボットか」
「見つかったら一斉に攻撃を仕掛けられるのは間違いなさそう」
「しかしどうやって出るか……」
従魔達は絶えずあるきまわっていて、足音が聞こえてくる。その数は五人を超えていた。
「音声に反応するのよね。それを使えないかしら」
一旦梯子を降りた迫間は端末機を取り出した。
「もしもし紫です。どうかしましたか?」
「敵の集中を一点に傾けたい。この端末機を敵地に投げ込んで音声を流せばそれができるが、そのためには協力がいる」
「ええっと、納得したのです。えっと、征四郎も考えていたのですが、征四郎のスマホに声を録音してリピート再生しておいて、スマホを投げるっていう事もできると思ったのです。さっき思いついたのですが」
「有効な手段だが、俺が録画したものを見れないというデメリットがある。動画を見終わった後なら、その方法で誘き寄せられるかもしれないな」
「むむ……。ではでは、迫間が通信機を投げ込んだら喋り続けていれば良いのでしょうか」
「なるべく大きな声で頼む」
「分かったのです。何を喋ろうか悩むのです……」
「俺が指示を出すまでは静かにな。早すぎると俺に注意が向く。俺が合図をしたら三秒後に声を出せばいい。問題ないな」
「問題ないのです。いつでも準備オッケーです」
梯子を登った迫間は、扉を開けて隙間を作った。その隙間から端末機をスライドさせて、部屋の奥に従魔の関心を惹きつける。
「よし、いいぞ」
リビング内を滑る端末機から、紫の声が響いた。
――今日の天気は晴れ後々曇りでー!
しかし一人だけの声ではない。今まで元気さを我慢していた六道の声も聞こえてきたということは、紫と頬をくっつけあって喋っているらしい。
――迫間さん頑張ってー!
不協和音が聞こえた。ほとんどのロボットが端末機に向かっている。迫間はすぐにリビングへと入り、手短な扉に入り込んだ。近くから新たな足音が聞こえて、箪笥の中に隠れた。この扉は家の廊下になっているようだ。
幾つかのロボットが目の前を通り過ぎる。数えてみれば十二体のロボットが駆けつけていた。リビングからは銃声が聞こえてくるが、変わらず通信機から声は聞こえている。
迫間の上手い調整で、端末は食器棚の下に入り込んでいた。ロボット達は食器棚を撃っているのだろう。
ロボットはもう通り過ぎないことが分かった。迫間は箪笥から出て、二階へと登った。
原因を探して二階に登っていたが、そこも徘徊したロボットだらけであった。廊下には二体のロボットしかいなかったが、部屋の中にはそれぞれ五体ずつ潜んでいた。一体何の部屋なのか調べる間もなく、調査は厳しいと断念させられた。
三階へと続く階段は廊下の先にあり、二体のロボットを掻い潜って登ると、両手扉があった。鍵は開いていた。耳を潜めても何も聞こえず、迫間は中に入った。
何本もの赤い線が見えた。すぐに線ではなく光だと気付いた。
「誰だ、お前」
書斎だ。窓から入る太陽の光が部屋の主を照らしていた。主は椅子に座って、迫間を見据えていた。
「こちらのセリフだ。ここは貴様の家ではないだろう」
「元々は人間の家だったんだろうが、乗っ取った以上私の住処だ」
赤い髪が床まで垂れ下がっている。煙管を吸っていて、黒い煙が上に登っていた。
「愚神……? 解せんな。貴様等が何故ここに居る」
「よく私が愚神だと分かったな」
「話を逸らすな。俺の質問に答えろ」
「立場を知れ」
椅子に座ったまま愚神は右手を前に突き出した。赤い線が迫間の頭一点に集中した。
「私は下僕を作るために拠点を探していた。そしたらここを見つけたのだよ。倉庫があるだろう。そこにガラクタ達が大量に眠っていた。それらを全て起動して、私のライヴスを注ぎ込んだ。忠実なる下僕の完成だ」
「やっている事はただの盗人だな。下らん」
「死にたいみたいだな、お前は。ところで犬を見なかったか? さきほどこの家に侵入してきてな。私の忠実なる下僕の仲間に加えようと思っていたのだが――」
迫間の背中から、声が聞こえてきた。
「それは私のことか」
スチャースだった。三階の書斎を訪れていたのはスチャースだけではなかった。書斎には赤城率いるエージェントの列ができていた。
「まさか首謀者が愚神だったなんてね……! 勝手に人の家に上がりこんで、不法侵入だよ!」
迫間は愚神に気づかれる前に、ハンディカメラで紫のスマートフォンに動画を送っていた。リビングのロボット達はまだ端末に夢中になっていて、すぐに救援に駆けつけたという話だ。
「数が増えたところで勝てると思うな。この部屋をなんだと思っている」
「何の部屋なのかしら」
迫間より前に出て、赤い線を集めた。部屋の至るところに固定砲台が隠れている。愚神は両手を挙げて固定砲台を表に露出させた。
武器は大量に潜んでいた。死角を作らないほどに。
「この部屋に来たのが間違いだったと後悔することになる。その後、犬は我が物となり、まずは近くの町にドロップゾーンを形成するのだ。お前らがいなくなった後にな」
「やってみろ」
赤城は不敵に笑った。
「後悔させてやる」
愚神も負けじと笑みを浮かべた。その手が橘に向けられると、全武器が一斉に狙いを定めた。そして自動的にトリガーが引かれた。
何が起きたのか、すぐには分からなかった。愚神の常識から外れたのだ。笑みが崩れ去るのも一瞬だった。
橘は全ての弾丸を反射したのだ。弾丸は元々置かれていた武器の所に戻る。その拍子に全ての武器は破壊されて、幾つかが大きな音を立てて床に落ちた。
「一体、何が……!」
「あなた、エージェントの事知らないのね。私達に勝ちたかったら、相手の研究をした方がいいわ。まあ、今回私達が敵になったのはあなたの運が悪かっただけ、なんだけれどね」
椅子から立ち上がった愚神は自ら橘に向かった。派手なコートと髪が地面を擦る。愚神は右手を使って、彼女に振りかざした。その手を止めたのは赤城で、橘はただ眼を瞑っているだけで十分だった。
すぐに愚神は地面に倒された。
「そんなもんかよ。大したことねえなあ」
「まだ終わらぬ。甘く見るな!」
愚神は腰から拳銃を抜いた。銃口を赤城の顎に向けたが、思いもよらぬ力が働いて腕が地面に落ちた。動かそうとするが、関節の部分に人形が乗っていて上手く動かせない。
「動けないでしょ?」
「ナイスだぜ六道! 歯ァ食いしばれよ。一瞬で散らしてやるぜ」
「阿呆め。一瞬で散るのはどっちだろうな」
「何だと?」
「私の体内には時限起爆装置が眠っていることを言っていなかったようだな。このまま散るのはお前の方だ!」
「自爆する気か!」
「ただで死ぬと思ったら大間違いだったみたいだな。さあ巻き込まれて死ね!」
時限起爆装置の時間は差し迫っていた。何人かは逃げられるだろうが、何人かは巻き込まれるだろう。スチャースは逃げなかった。六道はスチャースを抱きかかえて、愚神に背中を向けた。
「六道、何を!」
「任せて!」
爆発のタイムリミットは近い。
「終わりだな!」
しかしながら、突然愚神は書斎から姿を消すことになったのだ。突然、床に穴が空いたのだ。愚神は真っ逆さまに下に落ちていった。
「残念であるな、小官の眼は誤魔化せない」
下からソーニャの声が聞こえたその後に、爆発した。
●
帰路の途中で知ったことだが、ソーニャには愚神の爆発装置がレーダーで見えていたのだ。本来は敵性反応を確認できるものだが、その装置も敵として反応したのだ。愚神が自爆してから敵性反応が失せ、ロボット達は元の平和な性格を取り戻していた。
後からカグヤが廃屋に訪れて調査した。
スチャースの生まれた理由を先に知ったのはカグヤだった。その廃屋が一体なんなのか、棺のこと、スチャースという名前のこと、博士のこと、幸福の旅のこと。
一同は坂山のいる通信士の部屋に戻ってきた。坂山は全員にケーキを振る舞っていた。任務お疲れ様、を態度ではなく行動で示したということだ。
「晴海さん、ちょっといいかしら。例の研究所に関係する行方不明事件がないか調べてみたんだけれど、特になかったと報告がしたかったの」
「そうでしたか。杞憂だった、ということですね」
「晴海さんの予測が外れるだなんて珍しいこともあるものよね」
「いえいえ、今回の予想は外れてくれて寧ろ喜ばしいことでした」
スチャースはソーニャやエスティア達の玩具になって遊ばれている。スチャース本人は楽しそうにしていた。
「坂山、これを見るのじゃ。マクランという助手の日記じゃ」
カグヤは晴海と話す坂山の手に、日記帳を渡した。日記は今から八年前から昨年までが記されていて、ほとんどが人工知能と感情に関する研究だった。しかし時折、私生活に関することも楽しげに書いてあるのだ。
八年前にスチャースと遊んだと書かれていた。
――スチャースは偉い子です。博士の子供だと言われても納得いきます。心の広い博士の子供ですから、当然といえば当然でしょうか。今日は一緒にゲームをして遊びました。彼はゲームが好きなのですね。
「博士の子供の名前だったのですね。スチャースというのは」
ヴァルトラウテ(aa0090hero001)が言った。
「それが一体どうしてロボットの名前になったのか……は分かるのでしょうか」
「見れば分かるのじゃ。見れば」
――どうやら人工知能を悪く見る人たちがいるみたいです、この町には。宗教団体でしたが……。今日、家に押し入って研究を中止しろと言ってきました。博士はその時は了承していましたが、その内研究所を新しく作るのだと言っています。
そちらを別荘にするとも。博士はそちらに住むみたいで、家族とは少し別居の形を取るということでした。家族が危険になるからと。
――研究所には僕もついていきました。暮らし始めて一週間ですが、博士はもうホームシックになっています。僕は可笑しくて笑ってしまうのですね。日記を書いてる今も思い出し笑いをしちゃって。
それで我慢ができないというので、ゲーム機を買ったんです。スチャース君が好きな。コントローラーも二つ買って、僕と二人で遊んでます。
ああ勿論、家には戻ってるんですよ。ですが研究所の場所が知られてしまうかもしれないからって、研究所と家を繋ぐ道を用意するみたいです。
「それが、あの地下の隠し通路だった」
「あの廃屋は博士の家だった。家族の家でもあったというのですか」
「問題はここからじゃ」
カグヤは続きを促した。
――最悪だった。
その日の日記はその言葉だけで終わっていた。
最悪な内容はその次の日に記されていた。
――家で殺人事件が起きていた。犯人は宗教の狂人が起こしたもので、僕は激怒していた。犯人の顔を見た時は殴ってやろうかと思った。
博士はノイローゼになって研究をしなくなっていた。三階の自室ベッドで寝るだけの日々が続いていた。僕は食事を作っているが、あまり食べてくれない。本当に最悪だ。
――研究が再開しましたが、僕は博士も狂人になってしまったのだと思いました。彼は人の脳を使って人工知能を作ると言うのです。宗教団体から人を攫ってその脳を摘出して。でも僕は必死で止めました。
博士は言うことを聞いてくれました。しかし研究は続けなければならないと、自分の脳を使うのです。
――博士は研究をする度に壊れてしまうのが目に見えました。なぜなら、自分の脳を使った実験と研究を重ねていくうちに脳が狂い始めるのは、誰でも分かることだからです。まるで認知症になってしまったかのように、ボケてしまいました。
食事の時にスプーンを落っことす博士の姿は、信じられないくらい、心に突き刺さりました。もう日記を書くのはこれまでにします。
突然日記は白紙になった。カグヤはこう語った。
「おそらくスチャースという名前をつけたのは、自分を慰めるためじゃ。蘇生を行おうとしたのじゃろう。愛人のユリヤの蘇生も行おうとしていたみたいじゃが、先はスチャースじゃった」
「――スチャースはその事、知ってるのかしら」
「全部知ったのじゃ」
生まれた意味とはなんだったのか。事実を知っても答えはなかった。一体なんのために生み出されたのかを答えてくれるのは博士だけだろう。その博士はもう居ないのだから、結局スチャースの知りたかった真実は分からないままだった。
「あの誕生日ケーキはどういう意味だったのかしら」
「それがよく分からないのじゃ。廃屋も研究所も調べてみたんじゃが、手掛かりは一つもなくてのう。誰があそこに置いたのか、不明のままじゃ」
自分は博士の慰み者として生み出されたと知った時、スチャースは言葉を失っていた。複雑な気持ちであったのだろう。
博士は自分を作ろうとしていたのではない。スチャースという子供を作ろうとしていたのだが、スチャースは、自分が子供ではなく全く別の存在であることをよく、理不尽な程に知っている。
その時スチャースはこう言った。
「私は強く生きていく。この事実は私を大きく傷つけるものだった。だが生きなければならないと同時に思ったのだ。オブルグ博士、スチャース、ユリアが幸福を失った代わりに、幸福を探すのだ」
今彼は、笑って遊んでいる。
生きるために笑うのか、笑うために生きるのだろうか。そんな問答をしながらだった。
「坂山、あの廃屋にあったガラクタとかは持って帰ってもいいかのう? 有効活用できるかもわからんに」
「分かったわ。ところでスチャースの作り方とか、そういう資料はあったのかしら」
「うーん研究レポートがあったことにはあったんじゃが、全部失敗しておってのう。成功のレポートを探したんじゃが無かった。残念ながら一家に一台、マスコットキャラスチャースは遠い先の話になりそうじゃ」
カグヤが話し終えてから、晴海は思い出したかのように言った。
「町長と話している時、彼はスチャースをおチビと言っていました。多分、亡くなった息子さんの事を言っているんだと思います。私は生きていると嘘をついてしまいましたので、誤解を解いてきますね」
「早めに解いた方が良さそうじゃな」
晴海は部屋を出て、廊下で町長の部屋に通話をかけていた。部屋の外に出ているから声は聞こえないが、難しい行動だ。嘘をついた事を詫びて、人の死を伝えているのだから。
「彼も大変だったのね」
マイアはスチャースを見て言った。
私は強く生きる。
結局事実を知ったところで、私は何も得られなかった。ただ凄惨な過去を知っただけだった。博士は私を作るために全てを犠牲にして、寝たきりの状態になった。そこまでの価値があったから、そうしたのだ。
私も自分の身を犠牲にしてまで――その価値を見出す物を見つけたいと思った。
六道はそういえば、愚神が自爆をしようとした時に身を犠牲にして守ってくれたか。今回私とは初対面だというのに、本当に良い人だと感じざるを得なかったな。
今までの私は古いスチャースとして、過去に置き去りにしよう。
今日からまた新たに、幸福を探し始めるのだ。そのためにまずはこの言葉を言わねばなるまい。
少し照れくさくはあるが。
私を助けてくれてありがとう、エージェント。おかげで私は新たに生まれ変わるのだ。
知っているだろうか。幸福とは「ありがとう」から始まるのだ。
結果
| シナリオ成功度 | 成功 |
|---|




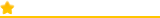
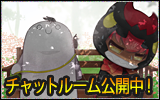



 1,500
1,500












